そもそもブリーダーとは?

ブリーダーとは、特定の動物の血統を繁殖させ販売する専門家のことです。ペットの世界では、主に犬や猫を対象とし、それぞれの犬種や猫種が持つ理想的な姿や性質(スタンダードと呼ばれます)を後世に伝える重要な役割を担っています。
ただ単に動物を増やすのではなく、遺伝的な病気を考慮しながら、より健全で、その品種らしい特徴を持った個体を育てるための深い知識と技術が求められます。
ブリーダーは、新しい飼い主が見つかるまで、親動物と子犬・子猫の健康管理や社会性を育むためのしつけも行います。
ブリーダーになるには?一般的な流れを解説

ブリーダーという職業に就くために、特定の学歴が必須とされるわけではありません。しかし、動物の命を預かる専門職であるため、体系的な知識と実践的な技術を身につけることが一般的です。そのための道筋は大きく二つに分けられます。
一つは、ペット関連の専門学校や大学で動物看護学、繁殖学、遺伝学などを学び、基礎知識を固める方法です。
もう一つは、現役のブリーダーのもとで弟子入りや研修、あるいはスタッフとして働きながら、現場で直接的な指導を受け、実践経験を積んでいく方法です。
どちらの道を選ぶにしても、独立して開業するためには、後述する「動物取扱責任者」の資格要件を満たし、「第一種動物取扱業」の登録を必ず行う必要があります。
ブリーダーの仕事内容

繁殖
ブリーダーの仕事の中心として「繁殖」があります。健全な子孫を残すためのは、専門的な知識で繁殖計画を立てることが必須です。
それぞれの犬種や猫種が持つスタンダードの基準などを理解することが不可欠。たとえば、遺伝的な疾患を持たないか、血統的に近すぎないかなどを考慮して、組み合わせを慎重に検討した上で繁殖を行います。
例えば、トイプードルのような人気犬種では、毛色やサイズの遺伝に関する正しい知識が求められます。
母体と生まれてくる子の双方の安全と健康を最優先に考え、交配から出産そして育児まで、全てを管理し健康なペットを繁殖させることがブリーダーの仕事の根幹と言えるでしょう。
食事の用意と身の回りのお世話
ブリーダーは、繁殖以外にも飼育管理を行います。これには、栄養バランスの取れた食事の準備、犬舎や猫舎の清掃と消毒、適切な運動量の確保などが含まれます。
特に、子犬や子猫は体調を崩しやすいため、日々の観察を怠らず、わずかな変化にも迅速に対応できる注意力が必要です。また、親犬や親猫の健康維持も、健全な子を育てる上で極めて重要であり、定期的な健康診断やケアが欠かせません。
健康面の管理
動物たちの健康を守ることは、ブリーダーの最も重要な仕事の一つです。これには、獣医師と連携して行う定期的な健康診断、狂犬病や混合ワクチンなどの予防接種の計画的な実施、寄生虫の駆除などが含まれます。
万が一、病気や怪我が発生した際には、迅速かつ適切な処置を施さなければなりません。また、感染症の発生を防ぐために、飼育施設全体の衛生管理を徹底することも、多頭飼育を行うブリーダーにとって不可欠な業務です。
社会化トレーニング
生まれてきた子犬や子猫が、新しい家庭環境や社会にスムーズに適応できるよう、幼い頃から人や他の動物、様々な物音などに慣れさせる「社会化トレーニング」を施します。
例えば、柴犬のような日本犬は警戒心が強い傾向があるため、早い段階で人との触れ合いに慣れさせることが、将来的な問題行動の予防につながります。この社会化期に適切な経験を積ませることは、動物が一生涯にわたって幸せに暮らすための基盤を作る、非常に価値のある仕事です。
飼い主へのアフターフォロー
ブリーダーは、育てた子犬や子猫を新しい飼い主へ引き渡す役割も担います。購入希望者に対して、その品種の特性、飼育上の注意点、しつけの方法などを丁寧に説明し、その人が本当に終生飼育できる環境にあるかを見極める責任があります。
販売はゴールではなく、むしろ新しい関係のスタートです。引き渡し後も、飼い主からの相談に応じたり、飼育に関するアドバイスを提供したりするなど、長期的なアフターフォローを行うことが、信頼されるブリーダーには求められます。
ブリーダーの平均年収

ブリーダーの平均年収は、その運営規模や形態によって大きく異なり、一般的には300万円から400万円程度が一つの目安とされています。
ただし、これはあくまで平均値であり、専業か兼業か、個人経営か企業に所属するかによって収入は大きく変動します。
例えば、副業として小規模に始めた場合の年収は100万円未満のこともあれば、大規模な施設で希少な犬種を扱い、ドッグショーなどで高い評価を得ているトップブリーダーでは、年収1000万円を超えるケースも存在します。
年収を上げるための方法
ブリーダーとして年収を向上させるためには、いくつかの戦略が考えられます。まず、繁殖する動物の専門性を高めることです。
例えば、チワワやダックスフンドといった常に人気のある犬種に特化する、あるいは、まだ飼育頭数の少ない希少種を扱い、専門家としての地位を確立する方法があります。また、ドッグショーやキャットショーに参加し、育てた動物が高い評価を得ることで、その血統の価値を高め、結果として子犬や子猫の販売価格を向上させることができます。
さらに、自身のウェブサイトやSNSを活用してブランディングを行い、直接販売の比率を高めることも収益改善に繋がります。
収入を上げたい場合は「独立開業」という選択肢も…
ブリーダーとしての収入を追求する上で、独立開業は大きな選択肢となります。ペットショップやブリーダー企業に雇用されている場合、給与は安定しますが、大きな収入増は見込みにくい側面があります。
一方、自身で事業主として開業すれば、経営努力が直接収入に反映されます。もちろん、施設の維持費、動物の医療費、餌代といった全ての経費を自己負担するリスクは伴います。しかし、計画的な経営と質の高いブリーディングを両立できれば、会社員としての収入を大きく上回ることも夢ではありません。
独立開業には「第一種動物取扱業」の登録が必須となり、事業主として経営手腕も問われます。
ブリーダーに必要な資格

ブリーダーという職業に就くために、「これさえあれば誰でもなれる」という国家資格は存在しません。しかし、動物の命を取り扱い、販売するという事業を行う上で、法律で定められた要件を満たすことや、自身の知識と技術を証明するための民間資格の取得が非常に重要になります。
動物取扱責任者
独立してブリーダーを開業するためには、事業所ごとに必ず1名以上「動物取扱責任者」を選任し、配置することが法律(動物の愛護及び管理に関する法律)で義務付けられています。これは資格の名称というよりは、特定の要件を満たした人が就くことのできる役割や役職を指します。
この要件とは、獣医師の免許を持つこと、愛玩動物看護師の免許を持つこと、あるいは「半年以上の実務経験」と「特定の学校の卒業」または「特定の民間資格の取得」を組み合わせることで満たされます。
第一種動物取扱業の登録
ブリーダーとして動物を販売し、営利を得る活動を行うためには、事業所のある都道府県または政令市に「第一種動物取扱業」の登録を申請し、許可を得る必要があります。この登録なくして、ペットの販売を行うことは法律で禁じられています。
登録カテゴリーは「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養」の7種類に分かれており、ブリーダーは主に「販売」の登録を行います。この登録を受けるための前提条件として、前述の「動物取扱責任者」を設置していることが必須となります。
愛犬飼育管理士
ジャパンケネルクラブ(JKC)が認定する民間資格です。犬に関する幅広い知識、例えば犬学、犬の管理、繁殖、動物愛護関連法規などを学びます。資格を取得するにはJKCの会員になった上で、講習会に参加し、試験に合格する必要があります。
この資格は、ブリーダーに必須ではありませんが、「動物取扱責任者」になるための要件の一つとして認められています。そのため、実務経験が不足している人がブリーダーを目指す際に取得を目指すことが多い資格であり、犬に関する体系的な知識を持つ証明にもなります。
愛玩動物飼養管理士
公益社団法人日本愛玩動物協会が認定する民間資格で、ペット全般に関する知識を問われます。動物関係法令、人と動物の関係学、飼養管理、しつけ、繁殖、動物の健康管理など、学習範囲は多岐にわたります。通信教育で教材を学び、課題報告問題を提出後、認定試験に合格することで資格が取得できます。
この資格も「愛犬飼育管理士」と同様に、「動物取扱責任者」の要件として認められており、ブリーダーとしての信頼性や知識レベルを客観的に示す上で有効な資格の一つと言えます。
ブリーダー開業までの流れ
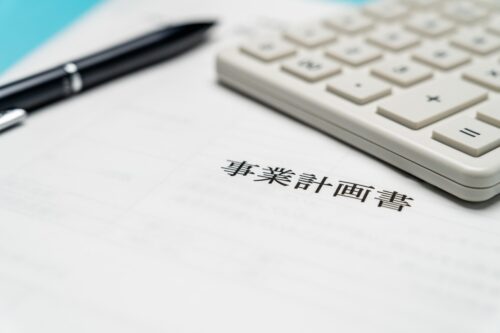
開業場所の確保
ブリーダーとして事業を始める最初のステップは、動物を飼育・繁殖させるための適切な場所を確保することです。自宅の一部を利用することも可能ですが、動物の鳴き声や臭いなどが近隣トラブルの原因にならないよう、十分な配慮が必要です。
また、飼育する頭数や動物種に応じた広さ、運動スペース、清掃しやすい床材、適切な換気設備など、「第一種動物取扱業」の登録基準で定められている飼養施設の構造や規模の要件を満たす必要があります。賃貸物件の場合は、ペットの飼育だけでなく、事業としての利用が可能かどうかを必ず確認しなければなりません。
必要な資格・実務経験
次に、事業を行うために法的に必須となる「動物取扱責任者」の要件を満たす必要があります。前述の通り、この要件を満たす方法は一つではありません。獣医師や愛玩動物看護師の免許を持っている場合は、その資格がそのまま要件となります。
そうでない場合は、「半年以上の実務経験」と「指定の教育機関の卒業」または「JKCの愛犬飼育管理士などの認定資格の取得」といった組み合わせで要件をクリアします。開業を決意した時点で自身の経歴を確認し、不足しているものがあれば、まずそれを満たすための行動計画を立てることが重要です。
必要な登録手続き・許可手続き
開業場所と動物取扱責任者の要件が整ったら、いよいよ行政への手続きに移ります。事業所を管轄する都道府県または政令市の動物愛護管理センターや保健所などの担当窓口で、「第一種動物取扱業」の登録申請を行います。
申請には、申請書、飼養施設の平面図、動物取扱責任者が要件を満たしていることを証明する書類など、複数の書類が必要です。申請後、担当職員による施設の立ち入り検査が行われ、基準を満たしていることが確認されて初めて登録が完了し、登録証が交付されます。この登録証がなければ営業を開始することはできません。
開業後の手続き
晴れて「第一種動物取扱業」の登録が完了し、営業を開始した後も、手続きは終わりではありません。個人事業主として開業した場合、事業を開始したことを税務署に届け出る「開業届」を提出する必要があります。
また、青色申告を選択する場合は、その承認申請書も併せて提出することで、税制上の優遇措置を受けることができます。事業が軌道に乗り、年間を通じて利益が出るようになれば、毎年確定申告を行い、所得税を納める義務が生じます。これらの税務関連の手続きも、事業を継続していく上で不可欠な業務です。
まとめ

ブリーダーという職業は、単に動物が好きという気持ちだけでは務まらない、深い専門知識と強い責任感が求められる仕事です。計画的な繁殖から日々の健康管理、社会性を育むトレーニング、そして新しい飼い主へと命のバトンをつなぐまで、その業務は多岐にわたります。
ブリーダーになるには、専門学校で学ぶ、あるいは現場で経験を積むといった道筋があり、独立開業するためには「第一種動物取扱業」の登録と「動物取扱責任者」の設置が法律で義務付けられています。収入は経営努力によって大きく変動しますが、質の高いブリーディングと適切な経営戦略により、大きなやりがいと共に経済的な安定を得ることも可能です。
この記事で解説した内容が、ブリーダーという職業への理解を深め、その道を志す方々にとっての確かな一歩となることを願っています。












