犬のUTIとは?症状と原因を知ろう
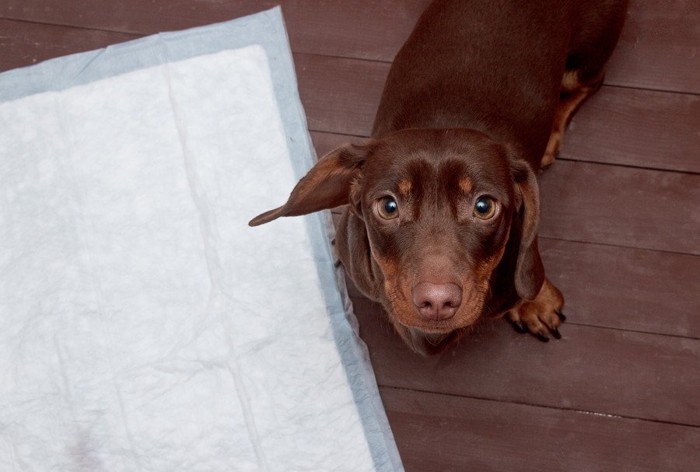
犬の細菌性尿路感染症(UTI)は、膀胱や尿道に細菌が感染することで発症し、犬の健康に大きな影響を与える可能性があります。最も一般的な症状には、頻繁にトイレに行く(頻尿)、排尿時の痛み(排尿困難)、血尿などがあり、特にメス犬や高齢犬では発症しやすい傾向があります。
国際小動物感染症学会(ISCAID)のガイドラインによると、UTIは以下のように分類されます
- 散発性膀胱炎:健康な犬に年に1〜2回程度見られる一過性の感染症
- 再発性膀胱炎:年3回以上の再発を伴う場合
- 腎盂腎炎:腎臓にまで感染が広がった重度のケース
- 前立腺炎:特に未去勢のオス犬でみられる前立腺の感染症
感染の原因となるのは、主に大腸菌などの腸内細菌で、免疫力の低下や排尿障害、尿路の構造異常などがリスク因子となります。
診断と治療の基本:抗菌薬は短期間が原則

UTIの診断では、臨床症状に加えて、尿検査(尿比重、細胞診など)と尿培養検査が重要です。とくに猫と異なり、犬の場合は症状と細菌感染が一致する可能性が高いため、経験的な抗菌薬治療(培養前の投与)も容認されています。
診断・治療のポイントの一つとして、尿は膀胱穿刺で採取することが理想的で、尿培養検査を行うことにより適切な抗菌薬の選択が可能になります。
治療の原則
ISCAIDガイドラインでは、以下のように治療の推奨がされています。
- アモキシシリンやトリメトプリムサルファ剤が第一選択(重症例を除く)
- 治療期間は原則3〜5日間
- フルオロキノロン系(例:エンロフロキサシン)は耐性対策のため慎重に使用
抗菌薬の変更は培養結果に基づいて行うべきであり、単なる効果不十分による切り替えは推奨されません。症状が改善した場合は、治療後の再培養は基本的に不要です。再発した場合のみ再評価が必要です。
慢性化・重症化する場合の対応:再発性UTIや腎盂腎炎

再発性膀胱炎や腎盂腎炎、前立腺炎など、より重度な症例では、診断と治療方針が異なります。
再発性UTIの管理
- 12か月以内に3回以上の発症が基準
- 原因疾患の特定が治療成功のカギ(尿道閉塞、腫瘍、ホルモン異常など)
- 抗菌薬の長期使用(7〜14日)が検討されるが、症状に応じて短期でも可
- 再感染と再燃の鑑別が必要
腎盂腎炎の対応
- 発熱、無気力、腎臓の痛み、脱水など全身症状が出現
- 血液検査や腎エコー、尿培養で確定診断
- 治療には腎組織に移行しやすい抗菌薬(例:フルオロキノロン系)を選択
- 治療期間は10〜14日間が推奨
前立腺炎
- 特に未去勢のオス犬に注意
- 長期間(4〜6週間)の治療が必要
- 去勢手術も再発予防に効果あり
まとめ

犬の尿路感染症は早期発見と適切な抗菌薬の使用が鍵となります。ISCAIDの最新ガイドラインでは、短期間かつ適切な薬剤選択による治療が重視されており、無駄な抗菌薬使用を避けることが愛犬の健康と公衆衛生の両方に寄与するとされています。













