輸血の必要性

皆さんは、輸血と聞くとどのような治療を思い浮かべるでしょうか。手術や怪我による大出血を思い浮かべることが多いと思いますが、その他にも輸血治療が必要となる病気はたくさんあります。
動物病院で輸血が必要となる主な病気を挙げると、血液凝固異常、免疫介在性血液疾患、悪性腫瘍、骨髄疾患、腎臓病、中毒、寄生虫疾患や交通事故などの外傷などになります。また、抗がん剤などの副作用で骨髄の機能不全に陥ったというような場合にも必要になることがあります。
今回は、犬の輸血や血液型、輸血の副反応などについて紹介します。
犬の血液型

血液型にはさまざまなタイプがありますが、人の場合はABO式とRh式が、猫の場合はAB式が一般的です。いずれも血液型の数が少なく比較的分かりやすいのですが、犬の場合はかなり複雑です。
犬はDEA式が一般的で、赤血球がどのような抗原を持っているかで血液型が決まります。現在広く認められている抗原の種類はDEA1.1、DEA1.2、DEA3〜DEA8の8種類ですが、研究が進むにつれ少しずつ種類が増えており、13種類以上あるといわれています。
犬の血液型はそれぞれの抗原の有無で表されますので「DEA1.1(+)・DEA1.2(-)・DEA3(-)・DEA4(+)…」のように表されます。
犬の輸血と血液型

人の場合、A、B、O、ABという4種類の血液型があり、輸血可否の組み合わせがあることはご存知の通りです。犬の場合も血液型による輸血可否の組み合わせがありますが、最も大きな要素となっているのがDEA1.1です。
DEA1.1(-)の犬にDEA1.1(+)の血液を輸血すると、体内で急性溶血反応という副反応を起こして生命の危機にさらされてしまいます。DEA1.1(+)の犬にDEA1.1(-)の血液を輸血しても問題は起きません。
DEA1.1間の不適合輸血の他にも、合わない血液を輸血してしまうとDIC(播種性血管内凝固症候群)や急性腎不全など、やはり命に関わる症状を引き起こす可能性があります。そのため、輸血前には交差適合試験(クロスマッチ)も行い、2点の安全性を確認してから輸血を行います。
日本の動物病院における輸血事情
アメリカと日本の違い
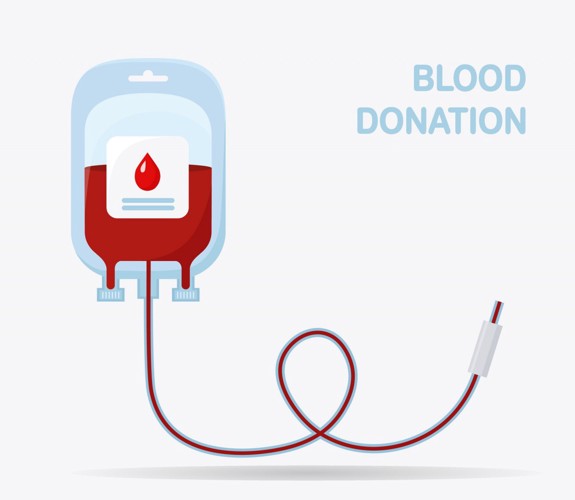
ペット医療の最先端と言われているアメリカでは、ペット用の血液バンクが設立されています。しかし日本にオフィシャルな犬猫用の血液バンクはありませんので、輸血が必要な場合にも受けられずに命を落としてしまうことも少なくありません。
普段は病院のペットとして暮らしながら、いざという時には患畜のために供血をする犬を数頭飼育している病院もあります。最近は、病院内で献血ドナーを募り、ボランティア犬によって血液を確保する病院もあります。
中には飼い主さん自らが自力で調達せざるを得ない場合もあるようです。いずれにしろ、輸血の確保は病院ごとに異なるのが日本の現状です。
献血できる犬の条件

病院で献血ドナーを募集している場合、多少の差はありますが、献血ドナーには概ね下記の条件が求められます。(健康であることは大前提です)
- 年齢:1〜7歳
- 性別:交配経験や予定のないオス、妊娠や出産経験のない避妊済みのメス
- 体重:15kg以上(20kg以上、10kg以上と病院によってかなり差があります)
- 予防:狂犬病ワクチン接種、混合ワクチン接種、フィラリア予防、ノミ・ダニ予防
最近は小型犬が多くなっているためドナーが減り、血液確保にはどの病院も苦労しているのが現状です。
中央大学では30年近く人工血液の開発に取り組んでいるという報道がありました。血液の機能のうち、酸素を運搬するという機能に特化して作られ、血液型を問わずに投与できるそうです。しかし、国の認可を受けるためにはまだ10年程度はかかるようです。
飼い犬の血液型を知っておくことのメリット

愛犬にも、いつ輸血が必要になるか分かりません。また、病気の時には正確な判定ができない場合もあるので、愛犬が健康なうちに血液検査を受け、DEA1.1の判定をしておくことは、決して無駄ではありません。
また、繁殖を目的としている場合は、新生児溶血を予防することもできます。新生児溶血とは、父犬がDEA1.1(+)で母犬がDEA1.1(-)の場合、生まれた子犬に母犬の初乳を飲ませると発生する溶血反応のことで、数日で死に至ることがあります。
まとめ

人と同様に犬も長生きできる時代になりました。その分、輸血治療が必要な犬も増えています。しかし、輸血に必要な血液の入手は困難なのが現状です。
愛犬にも、いつ輸血が必要になるかは分かりません。ですから、もしかかりつけの病院が献血ドナーを募集していて愛犬が条件に適合する場合は、ぜひ協力を検討してみてください。













