犬はどのくらいおしっこをしないと危険なの?

おしっこには、余分な水分と一緒に体の老廃物が含まれています。そのため、おしっこが出ないと体の中に毒素が溜まってしまいます。
おしっこの回数が少なくなっていたり、全然で出なくなってしまったときは病気の可能性もあるため、日頃から愛犬のおしっこの状態を確認することはとても大切です。
でも、どれくらいの頻度でおっしっこをするのが普通なのでしょう。何時間、何日おしっこをしなかったら病院で診てもらうべきなのか、分かりませんよね。もちろん個体差もありますが、ここでは基準となる量や頻度をご紹介していきます。
犬の一般的な1日の尿量の目安
健康な犬の1日の回数は、子犬:7~10回、成犬:3~4回、シニア犬:5~6回程度が目安とされています。
おしっこの量は、体重1kgあたり24〜41mlが目安といわれ、体重1kgあたり7ml以下になると乏尿、2ml以下になると無尿となり病気のサインであることが多いと言われています。
いつもより明らかにおしっこの量が少なかったり、全然出ていない場合は病気の可能性が考えられるため、早めに動物病院を受診しましょう。
1日以上おしっこが出ていない時は危険なサイン
犬がおしっこを我慢できる時間は年齢や生活習慣によって異なりますが、成犬で最大12時間程度と言われています。我慢出来る時間は子犬の時の方が短く、成犬になるにつれて我慢できる時間が長くなります。
全ての犬が12時間我慢できるわけではありませんが、環境が変わったり、お出かけをしていたりしたら長時間我慢している可能性もありますが、丸一日出ていない場合は危険な状態ですので注意が必要です。
犬は、1日おしっこが出ていないと「危険な状態」、2日出ていないと「命に関わる危険性がある」と言われています。丸一日おしっこが出ていない場合は、かなり緊急性があるのですぐに動物病院に連れて行きましょう。
犬がおしっこをしない原因

犬がおしっこをしないときには、環境の変化や脱水、病気などの理由が考えられます。処置が遅くなると命を落とす可能性も。病気が原因の場合、早期発見、早期治療がとても重要となります。
愛犬の様子や状況で、どんな原因があるのか確認することが大切です。いつもと違う場合は、おしっこが出ていないくらいと軽視することのないよう、早めに動物病院を受診しましょう。
ストレスやトイレ環境への不満で我慢している
自宅に迎え入れた初日、引っ越しや旅行、ペットホテルなどいつもと生活環境が異なる場合や、しつけ、性格によってもおしっこを長時間我慢してしまう場合があります。
外でしかトイレができない犬は、雨などでお散歩に行けないとおしっこができずに我慢してしまったり、きれい好きな犬の場合は、トイレが汚れていると我慢してしまうこともあります。
また、トイレの場所が変わったり、知らない人が来客していたり、外で工事などの大きな音がしている場合もストレスでおしっこが出来ないことがあります。日頃から愛犬の様子を確認して、おしっこが出ていない場合は原因を取り除いてあげましょう。
排尿トラブルを引き起こす病気を抱えている
尿道が詰まっている
尿の中にできた結晶や細胞などの成分が尿道に詰まってしまうことがあります。オスの方が尿道が狭いため、メスに比べて発症しやすくなっています。
また冬場は水を飲む量が少なくなり、尿が濃くなることで感染を起こしやすくなったり、結石が作られやすくなると言われています。
膀胱におしっこが溜まっていない
膀胱炎になっている場合、人間と同様おしっこが溜まっていないのに残尿感で何度もトイレに行ったり、血尿が出てしまうことも。
とくにメスの方が肛門と尿道口が近いため、細菌が尿道に侵入してしまうことが多くみられます。
腫瘍がある
膀胱、尿道に腫瘍ができると、尿道を塞いでしまい尿が出なくなることがあります。また、前立腺や子宮、膣など尿道の外に腫瘍ができた場合も、腫瘍が外側から尿道を圧迫して、おしっこが出にくくなる場合があります。
前立腺に異常がある
尿道の周りにある前立腺が腫瘍や膿腫などで肥大すると、尿道が圧迫されることでおしっこが出にくくなります。前立腺はオスのみにある臓器なので、メスでは見られません。
ヘルニア
会陰ヘルニアや鼠径ヘルニアにより、膀胱が本来ある場所から飛び出してしまうことがあります。膀胱がヘルニア孔から脱出すると尿道が曲がってしまい、おしっこが出にくくなってしまいます。
神経障害により排尿の指令が伝わらない
通常であれば尿が溜まるとトイレに行きたくなり、トイレで排尿します。この流れには、脳や脊髄などの神経が関連していますが、それらの神経が損傷すると排尿の指令が伝わらなくなってしまいます。
脱水症状
暑い日に十分に水を飲めなかったり、胃腸の調子が悪く下痢や嘔吐などで体内の水分が失われると、脱水症状を引き起こす場合があります。脱水症状が起こるとおしっこの量が少なくなったり、色の濃いおしっこが出ることがあります。
犬がおしっこをしない時に考えられる病気

おしっこが出ないときは、比較的緊急性の低い「環境の変化など」によるものや、緊急性の高い「病気によるもの」などが考えられます。
病気による場合でも、膀胱や尿道に関わるものだけではなく、それ以外の病気による可能性もあります。また、老犬や寝たきりの犬の場合は体力や筋力の低下により、うまく排尿ができないこともあります。
おしっこをしない理由には様々な原因が考えられますが、ここでは排尿しにくくなる可能性のある病気を5つご紹介します。
膀胱炎
膀胱炎は、細菌感染や膀胱結石、腫瘍などによって膀胱に炎症が起こる病気です。尿道が短いメスの方が発症しやすく、泌尿器系の疾患の中では多くみられる病気です。
頻尿、血尿、おしっこの姿勢をするが尿が出ないといった症状が現れます。また、膀胱結石や膀胱腫瘍が尿路を塞いでしまったり、膀胱炎の影響により剥がれ落ちた細胞や粘膜などが膀胱に詰まってしまうことがあります。
飲み水を十分に飲ませて、トイレを我慢させない環境をつくってあげることで、予防につながりますよ。
尿路結石
尿路結石は細菌感染や食事、ストレスなどにより、尿路(腎臓、尿管、膀胱、尿道)に砂粒から小石程度の結石ができてしまう病気です。
血尿や頻尿、痛みなどの症状がみられ、結石がおしっこと一緒に出ずに詰まってしまうと、おしっこが出なくなってしまいます。
食事などに含まれたマグネシウム、カルシウム、リン、尿酸などのミネラル分が尿中のたんぱく質などと結合して結石ができるため、食事での過剰なミネラル摂取を避けたり、十分に飲み水を与えましょう。
前立腺肥大
前立腺はオスの犬のみにある臓器なので、オス犬のみが発症する病気です。精巣から分泌されるホルモンのバランスが崩れることで発症すると考えられています。去勢手術をしていない中~高齢犬に見られることが多いです。
前立腺が肥大することで尿道を圧迫し、おしっこが出にくくなります。
慢性腎臓病
長い時間をかけて少しずつ腎臓の機能が低下し、老廃物が体内にたまってしまい、全身に障害を起こす病気です。シニア犬に多いと言われています。
初期段階では、飲水量や尿が少し増える程度の症状なため飼い主さんも気付きにくく、尿が出ない症状が現れたときにはかなり悪化している、ということも多いです。最悪の場合、命を落とす危険もある病気です。
定期的に健康診断を行うことで、早期発見につながります。
会陰ヘルニア
肛門のまわり(会陰部)の筋肉が薄くなり弱ることで、筋肉の隙間から脂肪や臓器が飛び出てしまう病気です。膀胱や尿道が飛び出てしまった場合、おしっこが出なくなることがあります。
外傷的なものでない場合は、中~高齢の去勢手術をしていないオスの犬がなりやすいと言われています。多くの場合は外科手術での治療となります。
また鼠径ヘルニアの場合も、膀胱が飛び出てしまったときは排尿困難になることがあります。
犬がおしっこをしない時に注意すべき症状
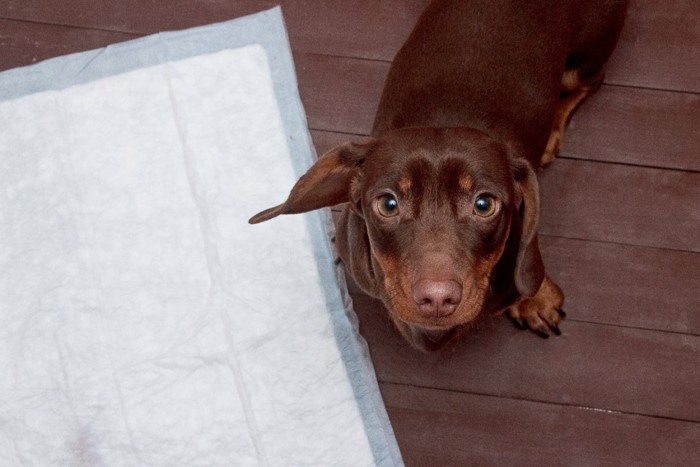
- 何度もトイレに行くのに、おしっこが出ていない
- おしっこに血が混ざっている
- おしっこにキラキラしたもの、石のようなものが混ざっている
- おしっこをするときに痛そうにしている(鳴き声をあげる)
- 食欲がない
- 下痢や嘔吐
- 口臭(アンモニア臭)
- むくみ
- 痙攣、意識障害
上記のような症状が見られた場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。おしっこが出ないままにしておくと、毒素が体の中に溜まって命に関わる「尿毒症」を引き起こす危険性があります。
おしっこが出ずに吐いていたり、口から独特のアンモニア臭がするなどの症状が出ていると、尿毒症の可能性があります。
日頃からトイレに行く回数、おしっこをするときの様子、おしっこの量・色・ニオイなどを気にするようにして、いつもと違うことがあったり、元気がない場合はすぐに動物病院に連れて行きましょう。
トイレシートを交換するときには、いつもとおしっこの様子が違わないか確認してみてくださいね。
犬がおしっこをしない時の対処法

おしっこをしないときは、基本的には動物病院で診察してもらいましょう。手遅れになれば命に関わる危険もあるからです。
しかし、病気やケガが原因ではなく、生活環境やストレスが影響している場合は自宅の環境を整えることで改善できる可能性があります。
ここでは病気による排尿困難ではなく、自宅で飼い主さんができる場合の対処法をご紹介していきます。
トイレの環境を整える
いつもと違う状況だと、おしっこができない犬も多くいます。トイレが汚れていたり、いつもと違う場所に移動されていると、犬にとってストレスになってしまいます。ストレスにならない環境を整えてあげることが大切です。
引っ越しなどで環境が変わったことでおしっこができなくなってしまった場合は、なるべく以前と同じような環境にトイレを置いてあげましょう。子犬の時と同じようにトイレトレーニングをしてあげると、徐々に慣れてくれますよ。
お外でしかおしっこができない犬は、雨の日や体調不良、シニアになったときのことを考えると、おうちでおしっこができるようにトレーニングするのも良いかもしれません。
食事や飲み水に気を付ける
ミネラルバランスの悪い食事をあげていると、尿中に結石ができる原因のひとつになります。
また、おやつや食事のトッピングが原因でミネラルの過剰摂取につながる場合もあるため、食事やおやつの内容を一度チェックしてみると良いかもしれません。
飲水量が減ることで、尿が濃くなり結石ができやすくなると言われています。特に冬場は、飲水量が少なくなる傾向があるため、何か所かに飲み水を置いたり、フードにスープをかけてあげたりしてみましょう。
圧迫排尿
高齢やケガなどにより、自分の力だけでは排尿が困難になることもあります。その場合には、お腹をマッサージするように膀胱を圧迫することで、排尿を促す方法があります。
ただし、圧迫しすぎると膀胱が破裂する恐れや、尿を膀胱から出し切れないと膀胱炎を引き起こしてしまうことも。必ず動物病院で指導してもらってから行うようにしましょう。
まとめ

たかがおしっこ、されどおしっこ。犬はおしっこが1日出ないだけでも、危険な状態になってしまいます。最悪の場合、命を落とす可能性もあります。
生活環境やストレスによる排尿困難もありますが、危険な病気が隠れている場合もあります。
愛犬が毎日どれくらいおしっこをしているのか、おしっこの様子はどうか、気にしてあげることでいつもと違う様子があれば早く動物病院に連れて行ってあげることができます。
トイレには行っているけれど、実はおしっこが出ていないという場合もあります。
トイレシートを交換する際に、いつもとおしっこの量は変わりないか、トイレの回数に比べておしっこの量が少なくないかをチェックしてあげることを習慣にすると良いかもしれませんね。
特に年齢を重ねると、体力や筋力が低下し排尿トラブルが起こりやすくなります。気付いた時には手遅れにならないように、毎日のケアや定期的な健康診断などで気を付けてあげましょう。












