犬のトイレに囲いは必要?

犬によってはスムーズにトイレを覚えることもあるでしょう。しかし、犬を迎え入れてはじめての問題の多くはトイレトレーニングです。
「トイレの場所は覚えているけど、うまくトイレシートの上でしてくれない」、「トイレシートの上で寝てしまう」、「壁におしっこをされて困る」など、犬種や性格、性別によってトイレの問題はさまざまなものが挙げられます。
結論を言えばトイレの囲いは設置したほうが良いですが、犬によって合わないこともあるため、愛犬の性格や性別などを踏まえて囲いを設置するかどうか判断することをおすすめします。
いずれにせよ、トイレに囲いを設置するのは犬のトイレトレーニングの問題を解決するための近道になるでしょう。
犬のトイレトレーニングの助けになる
トイレに囲いを設置することは、犬のトイレトレーニングの助けになるはずです。
室内で犬を飼うのであれば、トイレトレーニングは絶対に必要です。室内でトイレがうまくできなければ外でしか排泄ができなくなるでしょう。
犬が若いうちはそれでも良いかもしれませんが、高齢になって散歩に行くのが大変になったときに、室内でトイレを我慢してしまうことが考えられます。
また、トイレシートからおしっこがはみ出すという問題も囲いがあることで解決するはずです。囲いを設置すると、物理的にトイレをはみ出さなくなります。
片足をあげておしっこする犬にも対応できる
オスのほとんどは、片足をあげておしっこをします。これは、オスの縄張り意識によるもので相手よりも高い位置におしっこをすることで自分の体の大きさをアピールするという理由があるのです。
一方で、メスはお尻を下げておしっこをするという違いがあります。
外で片足をあげておしっこをする場合には問題ないですが、室内でも壁に向けておしっこをするオスは多いでしょう。
そんな場合もトイレの囲いは効果的です。囲いにトイレシートをかけて対処が可能ですし、片足をあげることによるおしっこの飛び散りも予防できるでしょう。
また、おしっこが飛び散ることで毎回掃除しなければならない飼い主のストレスも軽減されます。
犬が落ち着いておしっこすることができる
警戒心が強い犬は、囲いがあることで落ち着いておしっこができるというメリットがあります。
もともと野生で暮らしていたこともあり、警戒心が強い性格の犬は多いです。場合によっては、おしっこをしている無防備なときに外敵に襲われる心配もあるでしょう。
警戒心の強い犬は、視界の広い場所でトイレをすることを嫌がることもあります。しかし、囲いを設置することで犬は外敵に襲われる心配がなくなり落ち着いておしっこができるはずです。
室内でおしっこをしているときに外敵に襲われることはありませんが、犬の習性として、おしっこをしている最中でも気が抜けずにトイレの際に悪影響を及ぼす可能性もあります。
また、囲いを設置することで自分の匂いがこもり、安心できるという点も挙げられます。留守番時にも犬は自分の匂いを嗅いで安心するはずです。
囲いの素材によっては、防臭や消臭加工されているものもあります。飼い主としても、室内にトイレの臭いが充満せずに済むはずです。
トイレの場所を認識しやすい
囲いを設置することで、犬がトイレの場所を認識しやすくなります。特にトイレトレーニングが完了していない犬や、視力の低下してきたシニア犬には効果が期待できるでしょう。
囲いを設置していなければ、トイレシートに似た形状の新聞紙の上などで誤ってトイレをしてしまう犬もいます。そういった問題も囲いを設置することで解決することが期待できるでしょう。
犬のトイレの囲いの選び方

犬のトイレの囲いにはさまざまな種類がありますが、どれを選んだらよいかわからないという人もいるでしょう。
犬種やサイズ、性格や性別によって選び方は違います。ここからは、犬のトイレの囲いの選び方を解説します。
トレーや囲いのサイズに注意する
トイレトレーや囲いを選ぶ際は、サイズに注意する必要があります。犬の体のサイズに合っていない小さなトレーや囲いを選ぶと、おしっこがはみ出る原因になるでしょう。
また、小型犬に大きなトレーや囲いを設置するとおしっこがはみ出る心配は減りますが、落ち着いてトイレができないというデメリットも挙げられます。
犬はトイレの前にその場にくるくると回ってからトイレをするため、犬の体の2~3倍程度大きさを目安に選ぶと良いでしょう。
性別で選ぶ
オスであれば、きちんと囲いがついているものを選ぶことでおしっこの飛び散りを予防できます。また、トイレトレーニングが済んでいないメスの場合も囲いタイプのものを選びましょう。
トイレトレーニングが完璧にも関わらず、トイレシートでいたずらをしてしまう場合はトレータイプのものを選ぶことをおすすめします。
年齢に合わせたものを選ぶ
犬のトイレのトレーや囲いは、年齢に合わせたものを選ぶことも大切です。
シニア犬に段差の高いものを選ぶと、段差につまずいてしまう可能性があります。子犬であれば段差が高いとトイレだと認識しやすくなります。また、硬い素材のものはシニア犬の足の負担にもなるため、避けたほうが良いでしょう。
犬のトイレの囲いおすすめ5選!

次は犬のトイレの囲いのおすすめをご紹介します。それぞれの囲いの特徴やおすすめポイントを解説するため、購入時の参考にしてみましょう。
愛犬に合った囲いを探すのは意外に苦労するものです。いろいろな種類があり、どの囲いが愛犬に合っているのかわからない人も多いでしょう。
ここでは、犬種やサイズ、年齢などどんな犬に合うのかもご説明します。
アイリスオーヤマ トレーニング犬トイレ
〈おすすめポイント〉
- オーソドックスで人気のトイレの囲い
- スノコにより、犬のトイレシートのイタズラ防止
- 銀イオン配合で消臭効果が期待できる
〈商品の特徴〉
犬のトイレの囲いとしては、もっともオーソドックスなタイプといえます。トイレトレーニングが完了していない犬はもちろん、トイレトレーニングが済んだ後もスノコ部分を取り外して使い続けることが可能です。
銀イオンが臭いの元となる菌の発生を抑制することが期待できます。レギュラーとワイドの2サイズ展開でさまざまな犬種に対応可能なのも嬉しいポイントです。
有名メーカーなのでネット販売以外の方法でも入手しやすいでしょう。
OFT クリアレット
〈おすすめポイント〉
- 目立ちにくいデザイン
- 丸洗いOKで常に清潔にできる
- トイレシートのストッパー付き
〈商品の特徴〉
トイレトレーニングがある程度完了した犬は、このトイレトレーがおすすめです。高さがないため、片足をあげておしっこをするオスには不向きですが、おしっこの飛び散りが少ない犬に良いでしょう。
このトイレトレーは、透明で目立ちにくいデザインが特徴です。部屋の雰囲気を犬のトイレで崩したくないという人は、このトイレトレーを選ぶことをおすすめします。
ユーザー ペットフェンス
〈おすすめポイント〉
- 自由にパーツを組み合わせられる
- 留守番時のサークルとしても使用可能
- 使用しないときに片付けやすい
〈商品の特徴〉
愛犬のトイレの囲いを手作りするのが少し面倒くさいと感じる人は、この商品がおすすめです。自由にパーツを組み合わせて好みの大きさや形に調節することができます。
また、留守番時の一時的なサークルとしても使用できそうです。幅50cmのフェンスを組み合わせて作るため大型犬でも問題ないでしょう。
やわらかプラダントイレ
〈おすすめポイント〉
- ゆったりとした広さのプラダン製トイレ
- 出入口がバリアフリーでシニア犬にもおすすめ
- 底面にシリコンゴムシート付き
〈商品の特徴〉
大型犬でも安心してトイレができる、プラダン製のトイレです。たたみ半畳分の広さでどんな犬種にも対応できるでしょう。
また、出入口に高さがないバリアフリー構造で、シニア犬がつまずいてしまう心配もありません。底面にはトイレシートのズレ防止にシリコンゴムシートが付いています。
ゴムシートのおかげで犬がトイレの上をぐるぐると回ってもトイレシートがずれないでしょう。
やわらかプラダンおしっこガード
〈おすすめポイント〉
- オスにおすすめのプラダン製トイレ
- トイレシートを留めるためのクリップ付き
- 出入口がなくシニア犬にもおすすめ
〈商品の特徴〉
オスのために作られたプラダン製のトイレです。この商品があれば、犬が片足をあげておしっこをしても壁にかかってしまう心配がありません。
トイレシートを留めるためのクリップが付いているのも、嬉しい配慮です。> また、出入口がないタイプで子犬やシニア犬でも問題なく使用できるでしょう。
犬のトイレに囲いをする時の注意点

犬のトイレに囲いをする時はいくつかの注意点があります。
犬によっては、囲いをすることでトイレを嫌いになってしまう可能性もあるでしょう。メリットの多いトイレの囲いは、使い方によっては新たな問題点が浮上することもあります。
ここでご説明する注意点を守り、トイレトレーニングやトイレの問題をスムーズに解決しましょう。
犬のサイズに合わせて囲いをつくる
犬のサイズに合わせて囲いをつくることが大切です。小さすぎても大きすぎても、良くありません。
犬がゆったりとトイレができるサイズでありながら、大きすぎないものを選ぶようにしましょう。
オスの片足あげおしっこには高さが必要
オスには十分に高さのある囲いを設置する必要があります。囲いの高さが不十分だとおしっこが囲いの外に飛び散ってしまう可能性があります。
オス用にトイレの囲いを用意する時は、犬の体高以上のものを選ぶことがポイントです。
囲いが怖くなってしまう犬には少しずつ慣らす
臆病な性格の犬は、囲いを怖がってしまうことがあります。特に小型犬にとって囲いは高さがあり慣れていなければ恐怖を感じるかもしれません。
囲いが怖くなってしまった犬は、室内でトイレをすること自体を嫌がってしまうことが考えられます。そのため、怖がる犬に対して無理に囲いを設置する必要はないでしょう。
また、愛犬が臆病だと知っている場合には、いきなり囲いを設置せずに徐々に慣らせていく工夫が必要です。囲いを遠くから見せる、囲いの匂いを嗅がせる、囲いの中に入ったら褒めるなど、犬が囲いに対して恐怖を感じないように注意しましょう。
囲いの場所や種類をこまめに変えない
犬が囲いの中でトイレをすることを覚えたからといって、囲いを設置する場所や種類を変えてはいけません。
「トイレがいつもの場所にない!」とパニックになり、いままで完璧にこなしていたトイレトレーニングを一からやり直さなければいけない可能性も考えられます。
また、囲いから自分の匂いがして安心していた犬も、囲いの種類が変わることで自分の匂いがなくなり、不安を感じてしまうことがあるでしょう。
市販の犬のトイレの囲いが合わない場合は手作りしてみよう!
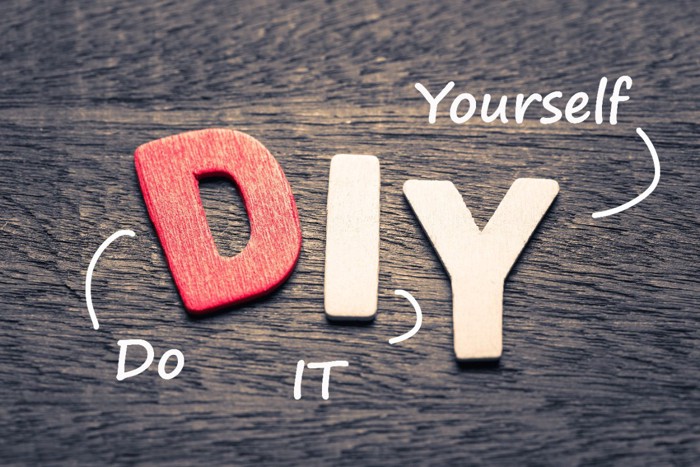
犬のサイズや性別によっては、市販のトイレの囲いが合わない場合もあるでしょう。そんなときには手作りがおすすめです。
DIYグッズは「犬のトイレ向け」として販売されているわけではありませんが、工夫次第で愛犬に合ったトイレの囲いを作ることができます。また、手作りをすることはさまざまなメリットがあります。実際の作り方についても見ていきましょう。
犬のトイレの囲いを手作りするメリットは?
犬のトイレの囲いを手作りするメリットとしては、下記の点が挙げられます。
- インテリアを考えておしゃれに作れる
- 愛犬の好みの大きさで作れる
- 安価で作れる
- 破損しても修理できる
- 用途に合わせて作れる
100円ショップで材料を揃える場合は、破損してもすぐに買い替えたり修理できたりする点が大きなメリットでしょう。また、市販にはないおしゃれなデザインなどもDIYグッズや素材によって作ることも可能です。
材料のプラダンは100ショップで揃う!
犬のトイレの囲いを手作りする時は、入手しやすいプラダンがおすすめです。プラダンとは、軽量プラスチックダンボールの略で100円ショップなどで購入できます。また、大きなものであればホームセンターでも購入できるでしょう。
プラダン以外に必要なカッターや強力な両面テープ、定規なども100円ショップで揃えることが可能です。また、プラダンの角の丸みを持たせるために、ボウルやお皿などがあっても良いでしょう。予算は千円も用意していれば十分です。
犬のトイレの囲いの簡単な作り方
実際にプラダンを使ってトイレの囲いを手作りするには、はじめにカッターと定規を使用して、プラダンを適切なサイズにカットします。
トイレの囲いに必要なものは、出入口と横面2枚、そして背面です。また、出入口部分の補強を踏まえて、出入口部分は同じサイズのものを3枚程度用意しましょう。
小型犬の場合は、横面と背面は幅約18cm、高さは約50cm程度あれば良さそうです。オスであればさらに高さを出すと良いでしょう。
出入口部分は、犬が怪我をしないように角をカットします。角をカットする際はボウルやお皿を当てながらカッターで切り、丸みを持たせましょう。また、出入口と背面を横面とくっつけやすいように、両端を5cmずつカッターで軽く切れ込みを入れて、直角になるように折り曲げます。
最後に、折り曲げた部分をそれぞれ両面テープでくっつけましょう。あらかじめ同じ大きさに切っておいた補強部分を、出入口と背面にくっつけて完成です。
この作り方は一例です。愛犬のサイズや作りたいデザインなど、安全性を最重視した上で好きに作っても良いでしょう。
▼「犬のトイレの基本」を知りたい方はこちら
まとめ
犬のトイレの囲いは、トイレトレーニングの手助けになったりおしっこがまわりに飛び散りにくくなったりとさまざまなメリットがあります。
また、シニア犬がトイレを見つけやすくなることも大きなメリットでしょう。
トイレの囲いは、犬のサイズや年齢、性別によって選び方は変わってきます。愛犬に合うものはどれかじっくりと探すことが大切です。愛犬に合うトイレの囲いがなければ、手作りをするのもおすすめです。
手作りのトイレの囲いは、100円ショップ等で手に入るプラダンを使用して簡単に作ることができます。デザイン性の高いものを作りたいときには、手作りを視野に入れても良いでしょう。


















