子犬がお散歩で歩かない理由

子犬のお散歩デビュー!これから愛犬と楽しく一緒に遊べるという、飼い主のわくわくと期待とは裏腹に、子犬が歩かない…ということはよくあります。子犬が散歩で歩かない理由は、次のことが考えられます。
怖がっている
子犬をお迎えして初めてのお散歩は、子犬の目の前に今まで見たこともない世界が広がっています。知らない人、行き交う車やその音、バイク、自転車、電車、歩いたことない地面、段差、マンホール、各所にある溝、色々な匂い等、一気に様々な情報が子犬の中に飛び込んできます。
そんなところにいきなり降ろされたら、怖くてどうしていいかわからず体が固まってしまうのは当然といえば当然ですよね。子犬にゆっくりと外の世界に慣れさせ、散歩は楽しい!と思ってもらえるようにしていきましょう。
首輪やハーネス、リードに慣れていない
今まで身につけていなかった、首輪やハーネス、リードといったものを急に装着させられて戸惑っている可能性もあります。この場合も、まずは子犬がそれらに慣れるところから始めていきましょう。
子犬を自分で歩かせる方法
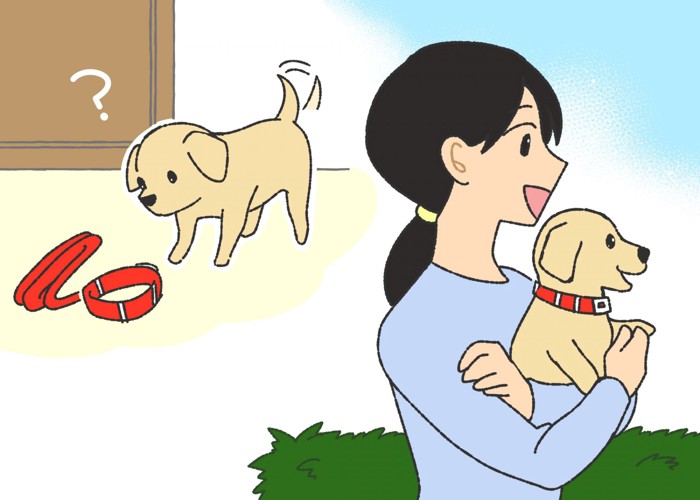
- お散歩道具の匂いを嗅がせる
- 家の中で首輪やハーネスを着けて遊ぶ
- 家の中でリードを着けて遊ぶ
- 抱っこして外の空気に慣れさせる
- 抱っこから地面に降ろしてみる
- 自分で歩くのを待つ(強制しない)
ステップ①:首輪やハーネス、リードの匂いを嗅がせる
まずは、家の中で首輪やハーネス、リードの匂いを嗅がせてあげましょう。子犬に、それらが危険なものじゃないということを知ってもらうところから始めます。
ステップ②:家の中で首輪やハーネスを着けて遊ぶ
匂いを十分に嗅がせて慣れてきたら、まずは首輪を優しく装着します。首輪を締める時はキツくなりすぎないように注意しましょう。首輪を着けた後に、指2本ほどの余裕があると良いと言われています。
ですが、頭が小さい、引っ張る力が強いなど個体差もあるため、子犬の様子を見ながら調整しましょう。首輪のサイズが合っていなくて嫌がるということもあるため、首輪のサイズは子犬に合ったものを選ぶことが大切です。
どうしても首輪を付けることを嫌がるという場合は、「バンダナ」を使ったトレーニングがありますので、詳しくは関連記事を読んでみてくださいね。
ステップ③:家の中でリードを着けて遊ぶ
首輪に慣れてきたら、リードを着けてみましょう。ここで注意するのは、リードを絶対に引っ張らないことです。まずは、飼い主がリードを持たずにただ着けている状態で慣れさせます。
子犬が装着されていることに慣れてきたら、飼い主がリードを持ってみましょう。絶対に引っ張らずに常にリードをたるませた状態にしてくださいね。
ステップ④:抱っこして外の空気に慣れさせる
いきなり子犬を地面に降ろして歩かせるのではなく、まずは外の空気に慣れさせるところから始めましょう。抱っこや、犬用カート(バギー)に乗せて近所を歩きます。
この時、「楽しいね~」「気持ちいいね~」など、子犬に優しく話しかけながら歩くと安心しやすくなります。
ステップ⑤:抱っこから地面に降ろしてみる
子犬が外の空気に慣れてきたら、地面に降ろしてみましょう。ここでのポイントは、とにかく褒めることです。その場に立てたら(歩けたら)、思いっきり子犬を褒めてあげましょう。おやつをあげるのもひとつの方法です。
ステップ⑤:自分で歩くのを待つ(強制しない)
子犬が歩かないからといって、無理にリードを引っ張らないようにしてください。無理に引っ張られることで、子犬が散歩は怖いものと思ってしまい逆効果になってしまいます。
子犬が立ち止まったら、自分で歩き出すまで待ちましょう。そして、子犬が自分から歩き出したらいっぱい褒めます。これを繰り返しましょう。
無理そうな時:あきらめて帰る
おやつを見せても食べようとせずに固まって歩かなくなってしまったら、それ以上は無理をさせずに抱っこやカート(バギー)に乗せて帰りましょう。
無理強いをして子犬が散歩を嫌いになってしまっては、本末転倒です。まずは子犬が無理のない範囲で、一連の流れを慣れるまで続けてみましょう。
子犬が散歩で歩かないという、予想外の出来事に飼い主も不安になります。ですが、飼い主の焦りや不安は犬にも伝わってしまい、余計に子犬の不安を増幅させてしまうことも。まずは飼い主が焦らず、どしっとした態度で気持ちを楽に長い目でゆっくり取り組んでいきましょう。
犬が散歩で歩かない理由【成犬編】

次に、散歩に慣れていたはずの成犬が急に歩かなくなってしまった時の理由をご紹介します。犬はなぜ、散歩中に突然歩かなくなってしまうのでしょうか?
それには次の理由が挙げられます。
怖がっている
何か大きな音がする、苦手な犬がいるなど、怖いと感じるものがあると人間と同様に、犬も恐怖で歩けなくなってしまいます。普段の環境と違って、人や車通りが多い、工事が行われているなどの要因が考えられます。
色々な環境に慣れていない子や、敏感で怖がりな子は、特に恐怖から歩かなくなる傾向にあります。この場合、犬は先を見て状況を伺うような様子を見せるでしょう。
かまって欲しい
本当は歩けるのにも関わらず、飼い主に構って欲しくてわざと歩かないということがあります。リードを引いても、その場に座り込んだり寝転がったりなどの態度を見せます。
疲れた
いつもより長時間の散歩になった時など、疲れから歩かなくなることがあります。また、老犬の場合はそもそもの運動量が減っているので、普段の散歩コースを歩いていても疲れが出て歩かなくなることがあります。
舌を出してハァハァと荒い息遣いだったり、ペタンと座り込んだりなど疲れている様子を見せます。
暑い・寒いに弱い
人間と同じで、犬も暑さ寒さに弱い子がいます。お散歩に出たものの、暑くて・寒くて歩かないということがあります。
暑い日は、アスファルトの温度が40~50℃近くまで上がります。犬は地面に近いところを歩いているため、人間よりも暑さの影響を受けやすいです。犬はその熱により、暑さでバテてしまい、呼吸が苦しそうだったり、体がいつもより熱くなるなどの様子を見せるなど、熱中症の危険性も。
寒い日は、被毛がシングルコート(上毛のみの一重構造)の子や、体の小さい小型犬は寒さの影響を受けやすいです。冷えた地面の影響で肉球が冷えて硬くなったりもします。この場合、歩かなくなって震えるなどの様子を見せるでしょう。
身につけているものが気に入らない
リード、ハーネス、洋服、レインコート、靴、エリザベスカラーなど、犬に身に着けさせたものが何かしらの理由で気に入らずに歩かなくなることがあります。
家を出てすぐのところで歩かなかったり、それらを身に着けた直後に歩かなくなるという様子を見せます。中には、最初は普通にお散歩していたのに、途中で急に歩かなくなる子もいます。
過去に嫌な経験をした
過去にその場所で犬と喧嘩した、飼い主に怒られたなど、何か嫌な経験をしたことを覚えていて歩かないということがあります。その場所に行きたくなくて、別の場所に行こうとする様子を見せます。
匂いを嗅ぎすぎている
犬は匂いを嗅ぐことで、情報収集を行っています。ですので、匂いを嗅ぐのは本能からの必要な行動で、ストレス発散にも繋がります。
しかし、ずっと同じところの匂いを嗅ぎ続けて歩かないということがあります。もしくは、匂いを嗅ぐ頻度が多くて全然前に進めないということもあるでしょう。
ケガや病気の可能性もある
散歩中に何かを踏んでしまったり、どこか傷めてしまったなどの理由から、急に歩かなくなることがあります。外傷が見られない場合は関節炎、股関節異形成、椎間板ヘルニア、骨折などの可能性もあります。
また、呼吸が荒くいつもより激しくゼーバーする様子があるなら、呼吸器系に異常がある可能性もあります。足を引きずる、歩き方がおかしい、いつもと息遣いがおかしいなどの様子が見られた時は、速やかに動物病院を受診するようにしましょう。
犬が歩かないときの対処法【成犬編】

お散歩中に犬が歩かなくなる理由には、色々とあることがおわかりいただけたでしょうか。
次に、犬が散歩中に歩かなくなった時の対処法についてご紹介します。
怖がっている場合
- 別のルートを歩く
- おやつやおもちゃで気をそらす
- 抱き上げてその場を通過する
犬が何かに怖がっている様子の場合、その場所を無理に通ろうとせずに別のルートでお散歩をしましょう。もし、別ルートでのお散歩が難しい場合は、犬が恐がる前におやつやおもちゃなどを見せて、なるべく恐いものから犬の注意をそらすようにしましょう。
用意したおやつやおもちゃを犬に見せ、鼻先辺りの位置に見せながらついてくるように誘導します。それでも歩かなくなってしまった場合は、犬を抱き上げてその場を通過するようにしましょう。
通過したらすぐに降ろしてあげてください。毎回同じ場所で歩かなくなるなら、散歩コースを変えることをおすすめします。
かまって欲しい様子の場合
- 声をかけたり抱き上げたりしない
- 犬の目線の高さでリードを軽く引く
- コマンド(進め、立てなど)をしつけておく
犬が飼い主に構って欲しい様子でわざと歩かなくなる場合は、声をかけたり、抱き上げたりすることは逆効果です。それをすると、犬は「歩かないと良いことがある」と理解し、同じことを繰り返すようになってしまいます。
また、犬は自分の要求が通ったことで、飼い主をリーダーだと思わずわがままになる可能性もあり、しつけをする上で望ましくありません。そんな時は、号令をかけて前に進むよう促します。「進め・立て」などのコマンドをしつけておくとなお良いでしょう。
それでも歩かない場合は、犬の目線の高さでリードを軽くクイッと引っ張ります。ここで、グイグイと無理やり引っ張るのは絶対にNGですので気をつけましょう。
疲れている場合
犬が疲れた様子で歩かない時は、安全なところで少し休ませてあげましょう。ただし、ここで抱っこをすると歩かないと構ってもらえると思い込み、わざと歩かなくなってしまうこともあるため、注意が必要です。
犬の疲れが回復して、自ら歩き出すまでじっと待つようにしましょう。また、次の散歩の時は、犬が疲れない程度の距離になるよう、散歩量を調整しましょう。
暑がっている・寒がっている場合
暑がっている様子なら、すぐに日陰に移動して休ませてあげましょう。もし、いつもより体が熱くなっている場合は体に水をかけたり、首元にアイスノンなどをあてて冷やしましょう。
何より、猛暑の中の散歩は、熱中症の危険性があるためできるだけ避けることが重要。朝や夕方などの涼しい時間に散歩するようにしましょう。休んで体を冷やしても苦しそうにしている時は、すぐに動物病院に連れて行ってください。
寒がっている様子の時は、そのまま無理に連れ出さずに洋服を着せるなどの防寒対策をしっかり行いましょう。寒いところに長時間いると、低体温症になる恐れがあるので注意が必要です。
リード、ハーネス、洋服が気に入らない場合
お散歩の時に初めて装着するのではなく、家にいる時から身につけるものに慣らしておくと良いでしょう。また、必ずしもハーネスでないとダメということもないため、首輪に変えてみたりなど、その子に合ったものを探してみてください。
匂いを嗅ぎすぎて歩かない場合
- リードを短く持って動きを制限する
- 匂いを嗅ぐポイントから距離をとる
- 匂いを嗅いでも良いポイントを決める
あちこちに意識が向かうと、犬が匂いを嗅ぎたい場所が増えてしまうため、リードを短く持って行動範囲を制限してあげると良いでしょう。
また、匂いを嗅ぎそうなポイントが近づいてきたら、できるだけ距離をとりましょう。そして、名前を呼んでアイコンタクトを取ることで犬の気をそらしてあげると良いです。
とはいえ、全く匂いを嗅がせないのはストレスに繋がるため、匂いを嗅いでも良いポイントを決めておくことをおすすめします。できれば、終了の合図を決めて、合図と共に匂いを嗅ぐのを止めさせるようにしつけると良いでしょう。
散歩で歩かない犬にやってはいけないこと
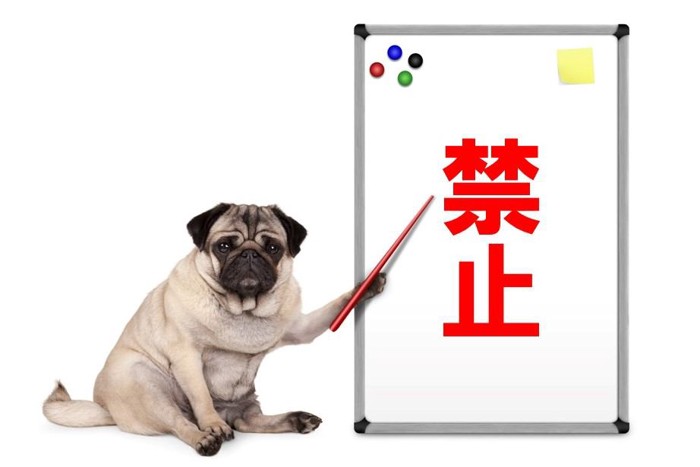
犬がお散歩中に歩かなくなった時に、やってはいけないことをご紹介します。
無理やりリードを引っ張る、怒る
一番やってしまいがちなのが、犬が歩かないからといって無理やりリードを引っ張ってしまうこと。無理に引っ張って引きずることで、犬が足を踏ん張った際に肉球を痛める恐れがあります。また、首や喉を痛める危険性もあります。
また、安易に怒ることもNGです。犬が歩かないのには何かしらの理由が必ずあります。その理由を探ろうとせずに、頭ごなしに怒ってしまうと、犬との関係性も悪くなってしまいます。
これらのことが嫌な体験として犬が記憶してしまうため、無理にリードを引っ張ったり、怒って歩かせようとするのは止めましょう。
安易に抱っこする
犬が恐怖を感じている場面で、どうしても歩かない場合は抱っこしてその場を通り過ぎる、という対処法もありますが、歩かない理由を見極めずに歩かなくなったらすぐに抱っこする、ということはしないようにしましょう。
犬が甘えて、抱っこして欲しいから歩かないという行動をとるようになり、逆効果になってしまいます。どうして歩かないのか、その理由や状況を見極めて適切なタイミングで抱っこという手段を取るようにしましょう。
犬の要求に従う
いつもの散歩コースから外れて犬が行きたそうな方向に進むなど、犬に決定権を与えることはやめましょう。それをしてしまうと、飼い主のリーダー権を失ってしまう恐れがあります。犬の思い通りにはさせないよう、しっかりと飼い主が主導権を握って散歩するようにしましょう。
▼「犬の散歩のしつけの基本」を知りたい方はこちら
まとめ

犬がお散歩中に歩かなくなるのには、必ず理由があります。もし、犬がお散歩で歩かない場合には周辺の状況をよく観察し、何が原因になっているのかを判断して適切な対応をとりましょう。
また、犬が何かを恐がって歩かない場合は、事前に恐がる可能性のあるものを避けられるよう、リーダーである飼い主が犬が苦手なものをきちんと把握しておくことも大切です。ただし、犬が恐がるものを避けてお散歩するのは、あくまでも応急処置的な方法です。
犬が外の環境に対して怯えることがないよう、子犬の頃からトレーニングを十分にしておくことが大切です。子犬の頃に地面を歩かせなくとも、抱っこをしてお散歩に連れて行くのも効果的です。そして、家族以外の人や他の犬とたくさん触れ合ったり、色々な音を聞かせる、車や電車が通る場所など、慣れさせることを心掛けましょう。
犬も飼い主も、一緒になってお散歩が楽しい時間になりますように。
















